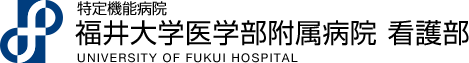看護師紹介
- すべて
- 認定看護師
- 専門看護師
- 特定看護師

廣澤 祐太感染管理

廣澤 祐太認定看護師
みんなで力を合わせて、みんなを守る
医療関連感染の発生は、患者さんの安全を脅かすだけでなく、関わるスタッフの健康や、病院全体にも大きな影響を及ぼします。昨今は専門性が高い医療が求められるなか、感染対策も日々新しく変化しています。感染は一人の力では防ぐことができず、関わる人みんなで力を合わせて取り組むことが重要です。感染管理認定看護師として、医療を提供する場で現実的に実践できる感染対策を、患者さんや病棟スタッフとの関わりを大事にしながら、縁の下の力持ちとなって、支えていけるような活動をしていきたいと考えています。

増永 唯クリティカルケア

増永 唯認定看護師
医療と患者視点に根ざした看護を
クリティカルケアは、生命の危機状態にある患者さんやその家族を対象とします。そのため救急・集中治療だけでなく、一般病棟において重症化リスクを抱く患者さんへのサポートも重要です。私たちは、症状や訴えを声に出せない患者さんの微細な変化に気付くことが求められ、その思いを支援する役割があります。専門知識を活かし、患者さんが安心して治療を受けられる環境を整え、患者さんが自分らしく生活し続けられるよう支援すること、これが私の目指す看護師像です。退院後の生活を見据えながら重症化予防と早期回復を支援し、多職種と連携し患者さんのニーズに応える看護を目指します。

村田 美穂老人看護専門看護師

村田 美穂専門看護師
“その人らしく生きる・逝く”を支える
人は誰でも、過去(これまでの人生)があり、現在があり、未来があります。高齢者は特に、過去が長く、未来が短い存在です。対象の医療や生活に関する過去を知り、それを踏まえて現在を捉え、できるだけ充実した日々を送りながら、限られた未来を、「その人らしさ」を基盤に対象と共に考えていく…そんな看護はとてもやりがいがあります。
また、現代において、高齢者看護の実践力を高めることは、看護のやりがい感や業務能率を高めることにつながると考えています。

大島 俊哉認知症看護

大島 俊哉認定看護師
その人らしいに寄り添って
認知症を患った方々にとって、入院することによって環境が大きく変わり、混乱をもたらすことが多々あります。また、自宅から離れ、慣れない環境の中、大きな不安を抱え、自宅ではできていたことができなくなることがあります。そのような方々が少しでも安心して、落ち着いた入院生活が送れるような関わりや、本人が持てる力を十分に発揮でき、自宅で過ごしていたように生活してもらうための関わりを行っていきたいと思っています。また、治療や療養場所の選択などご本人、ご家族の意思を尊重した支援を行っていきたいと思います。

畑 千尋皮膚・排泄ケア

畑 千尋認定看護師
必要、でも生きてきたスタイルを崩さないケアを一緒に考えたい
創傷、ストーマ、排泄における障害予防、改善のためのケアを専門としています。皮膚障害は長時間同一体位や医療機器の接触が原因となります。また、療養している患者の「見た目」でネガティブな印象を抱く家族もいます。皮膚障害予防に必要な処置だからとケアを強要しても続きません。患者がいままで生きてきたスタイルをできるだけ崩さないケアを考えて提供することは、皮膚障害予防、延いては患者の苦痛除去、家族ケアにも繋がると考えます。特定行為研修も修了し、慢性創傷における壊死組織の除去と陰圧閉鎖療法の実施も活動内容に加わりました。創傷を評価してタイムリーに行為を実施できるため、創傷の悪化予防や早期治癒が期待できます。

カテーテル管理チーム

カテーテル管理チーム特定看護師
カテーテル管理チームでは、末梢留置型中心静脈カテーテル(PICC)の挿入と中心静脈カテーテルの抜去を実践しています。特定看護師がタイムリーにPICCの挿入を行うことで、スムーズな治療につながると考えます。また、医療において血管内留置カテーテルは必要不可欠なものですが、感染などの合併症が起こると、治療期間が長引き、入院期間が延長されることがあります。そのため、適切なカテーテル管理ができるよう関わっていきたいです。

創傷管理チーム

創傷管理チーム特定看護師
私たちは創傷管理のエキスパートとして「褥瘡または慢性創傷の治癒における血流のない壊死組織の除去」と、「創傷に対する陰圧閉鎖療法」の2行為を実践しています。
創傷の治癒、治療期間の短縮化を図ることを目的とし、看護師ならではの視点を踏まえ、患者が治療を継続できるよう苦痛を最小限にした処置を心掛けています。また、治療中のケア、創傷発生・再発への予防的ケアに関する看護師教育にも力を入れています。

重症患者対応チーム

重症患者対応チーム特定看護師
当チームは、呼吸器(気道確保に係るもの・人工呼吸療法に係るもの)関連および動脈血液ガス分析に関連する特定行為を実践しています。組織横断的な活動の中で医療・看護の両面から患者をアセスメントし、チーム医療の推進に貢献しています。特定行為を実践するだけでなく、これらの行為を重症患者へのケアに積極的に結び付け、重症化の予防と早期回復を図ることで、患者のより良い予後に貢献することを目指しています。

竹原 和樹救急看護

竹原 和樹認定看護師
~防ぎえた死亡をなくす~
防ぎえた死とは、医療が適切に介入すれば避けられた可能性のある死のことです。
日本では2011~2017年の調査で院内心停止の発生率は入院患者1000人当たり約5人と報告され、これは決して少ない数字ではないと思います。防ぎえた死を起こさないためにも、急変を起こす前段階で察知し状態悪化を防ぐ取り組みが非常に重要です。また、もし心停止に至ったとしても適切な救命処置によって命を救うことを目指す必要があります。そのために私たちは重症化予防・急変対応能力の向上といった取り組みに力を入れています。患者の近くにいる私たち看護師だからこそ、患者の状態の変化を機敏に捉え、防ぎえた死をなくしていくことができると信じています。

術中麻酔管理チーム

術中麻酔管理チーム特定看護師
当院では、特定行為研修を修了した看護師が、術中麻酔領域において医師の指示のもと高度な看護ケアを提供しています。周術期管理の一環として、術中の気道、呼吸管理や輸液・循環管理などを行い、患者様の安全を最優先にサポートしています。チーム医療の一員として迅速かつ的確な対応を心がけ、質の高い医療の提供に努めています。安心して手術を受けて頂けるよう、引き続き充実を図ってまいります。

高島 和也感染管理

高島 和也認定看護師
ともに考える感染管理をめざして
感染管理認定看護師の役割は医療関連感染を予防、管理することです。患者、家族だけでなく従事する職員から施設全体、地域とさまざまな相手を対象としています。我々の生命を脅かす感染症に対して適切に感染対策や予防行動ができているかを管理する力が求められています。手指衛生などの基本的な感染対策行動は、感染症発生時のみならず、どのような場面でも必要な手技であり、習慣化のためには継続した取り組みや意識変容を促すことが必要です。正しく理解し、正しく実践できるように支援しなければなりません。職員が実際の業務の中で実践可能な方法をともに考えていくことのできる認定看護師を目指していきます。

道関 沙緒理糖尿病看護

道関 沙緒理認定看護師
共に歩んでいく支援
糖尿病は生涯にわたるセルフケアが必要とされる慢性疾患であり、糖尿病の患者さんは、社会のさまざまなことに関わりながら生活をし、並行して糖尿病の治療を続けています。そのような患者さんの頑張りを、より専門性をもって支援していきたいと思い、認定看護師を目指しました。
糖尿病の患者さんが自宅で安定した療養生活を送るために、患者さんの生活を知り、価値観や思い、経験を尊重しながら患者さんと向き合い、具体的な方向性や方策を患者さん自身が見いだせるように、共に歩んでいけるような支援をしたいと思っています。

広瀬 知美小児看護
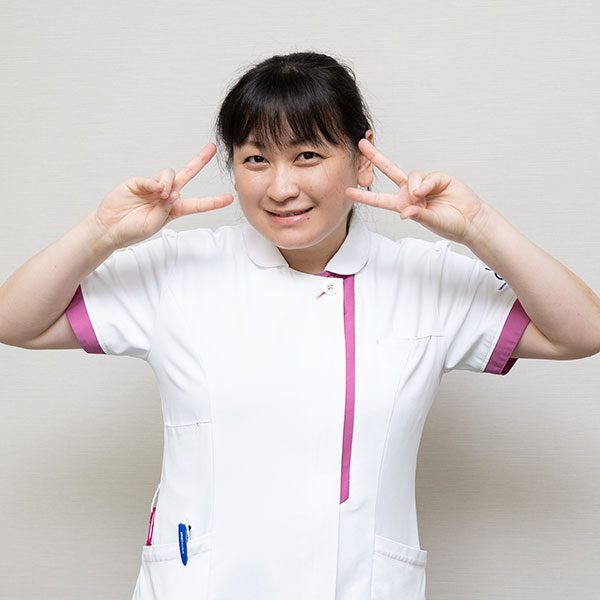
広瀬 知美専門看護師
子どもと家族の笑顔のために、ともに寄り添う看護を
小児看護は、患者である子どもだけでなく、両親やきょうだいなど家族への看護も大切となります。辛く苦しい闘病生活を行う子どもたちが少しでも笑顔になり、入院生活を過ごせるように支えたいと思います。子どもの目線に立ち、しっかりとコミュニケーションをとり、過ごしやすい雰囲気を作り、子どもの成長・発達に合わせた看護を目指しています。そして、子どもの闘病生活を支えている家族の不安を少しでも取り除けるように、家族との信頼関係を築き、ともに悩み考え、家族の思いに寄り添った看護が実践できるように関わっていきたいです。

石塚 匡晴精神看護

石塚 匡晴専門看護師
患者さんのこころとからだを総合的にとらえた質の高いケアを
近年、身体疾患治療のために入院する精神疾患を持つ患者さんや、身体疾患治療の過程で精神的な問題を新たに抱える患者さんは、決して少なくありません。身体疾患の治療過程における様々な要因によって、精神症状が表れた場合、患者さんの苦痛は大きく、一方で関わる医療者も大きな困難さを感じることがしばしばあります。そんなときに医療者が患者さんの精神と身体を総合的にとらえられるよう支援したり、専門的な精神科的治療と看護を提供することを活動として行っています。私の活動によって、患者さんの苦痛と医療者の困難さが軽減し、患者さんと医療者がベストな状態で治療に臨んでいけるようになるための支援ができればと思っています。

大嶋 理恵専門看護分野 災害看護/認定看護分野 救急看護

大嶋 理恵認定看護師専門看護師
日々精進、全ては患者や家族、地域の為に
救急初期治療や災害看護の急性期は患者や家族と接する時間が短いため、ゆっくり考えて行動できることは少なく、それまで学んだ知識やスキルを短時間で行動に移さなければなりません。そのために、取得した後も、最新の知識を取得しトレーニングを継続することを心がけています。日々の努力は大変ですが、それが後に患者や家族のためになったときの充実感には代えられません。皆さんと知識やスキルを共有し、一緒に働けることを楽しみにしています。

林 智美救急看護

林 智美認定看護師
当たり前の生活を守っていく
救急患者は時と場所を選ばず発生し、対象は疾病、外傷、脳血管障害、中毒などの多種多様な疾病・外傷を有したあらゆるライフステージの患者とその家族です。事故や急な病気、慢性疾患の急性増悪は患者・家族にとって、日常から非日常に強制的に変化させられる瞬間です。
情報の少ない患者をフィジカルアセスメントや受傷状況等で判断していくため、私たちの関わりが患者の生命の維持や生活の質を左右する可能性があると言っても過言ではありません。そのため、学習を継続し、自己・チーム力を高めていく必要があると考えます。それが、患者の当たり前の生活を守っていくことにつながると信じています。

桒原 勇治集中ケア

桒原 勇治認定看護師
患者の回復を妨げない。
集中治療室に入室される患者は、生体に過大な侵襲を負っています。そして、生体は自分自身で一生懸命回復しようとしています。私たち看護師は、その回復を手助けしなければなりません。しかし時として、私たちが良かれと思って行う看護ケアが実は患者にとって非常に大きなストレスとなっていることがあります。それは、患者の回復を妨げていることになります。そのため、私たちは患者さんの声にならない声(訴え)をモニターの数値や波形から、そして自分の五感を最大限に駆使して観察し、アセスメントし、そのケアが患者にとって必要なものなのか、有害となるのかを判断していく必要があります。

圖子 博美クリティカルケア

圖子 博美認定看護師
早期回復のために
近年の超高齢化社会、生活習慣病の増加とともに病態が複雑化、重症化する患者さんが増加しています。集中ケア認定看護師はそのような重症患者さんが合併症なく早期に回復し、自分らしい生活を送ることができるように看護を行います。患者さんの重症化のサインに気づくことができるのは常に患者さんのそばにいる看護師です。病気は治ったけれど食べることができない、歩行できないなどの辛い思いをする患者さんが少しでも減るように一緒に頑張りましょう。

浦井 真友美乳がん看護

浦井 真友美認定看護師
女性に優しく、家族に頼られる。
乳がんは、女性の臓器別がん罹患率の第1位です。患者さんの年代も30歳から80歳代までと様々で、女性として家族、仕事、家事などの重要な役割を持っています。同じ女性として家事や仕事を続けながら治療が続けられるように、様々な治療に伴うケアを通じて患者さんの不安や悩みに優しく寄り添い、よりよい療養生活のための情報提供を行い、患者が乳がんと共に生きていくのを支えることを目指しています。乳がんの患者さんは、治療をしながら家事や育児にがんばっています。だからこそ、患者さんの家族にも積極的に関わり、家族と共に患者さんのことを考えていくことを目指したいと思います。

髙野 智早がん性疼痛看護/がん看護専門看護師

髙野 智早認定看護師専門看護師
寄り添う 信じる
自施設は大学病院という特徴から、多様な病期および治療経過のがん患者さんがおられます。そのため告知後のショックや治療に関連した苦痛、終末期の緩和困難な苦痛などの複雑なつらさを抱えた患者さんを前に、医療者もまた苦悩することがあります。私が所属する「緩和ケアチーム」は主治医と看護師を支える役割を担っています。患者さんやご家族はもちろん、主治医や看護師が困った時に、身近な相談者となれるよう心がけています。また、今後は臨床だけでなく研究や教育にも力を注き、最終的に緩和ケアが当たり前の医療となり、患者さんに質の高いがん医療が提供されることを目標に活動していきたいです。

笹川 良明がん性疼痛看護

笹川 良明認定看護師
主役である患者さんと共に
がんによる痛みは、診断時には3割の方が経験されています。また、身体的な症状だけではなく、病気や治療、日常生活に対しての不安や家族や仕事などに対しての心配など、様々な苦痛も生じます。これらの痛みを緩和する事は、自分らしい日常生活を送るためにはとても重要な事です。日常生活の支援が役割の看護師が疼痛の緩和に関わる事は、患者さんの生活の質の向上にとても重要です。
人間の生と死についての関わりも少なくない分野ですが、その関わりから看護師として、また人としてさらに学ばせていただく機会を頂いていると思います。 患者さんと共に苦痛に向き合い、その苦痛の緩和のお手伝いが出来る様な看護を目指していきます。

徳原 涼衡がん放射線療法看護
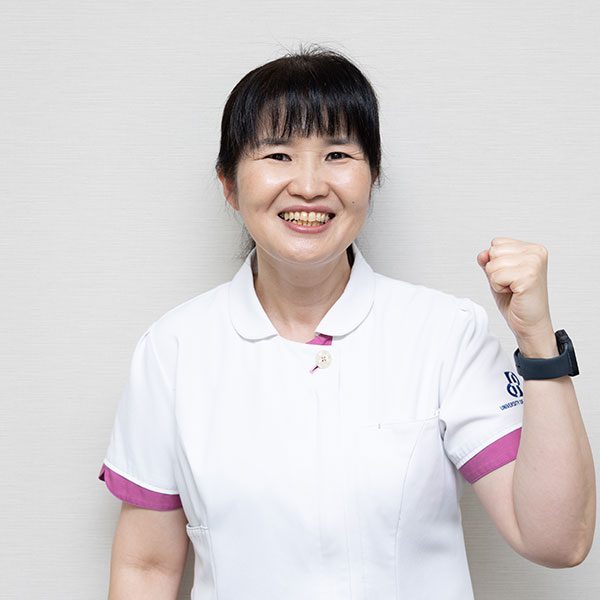
徳原 涼衡認定看護師
放射線療法を選択した人々の身近な存在として出来ること
放射線療法は、現在、がん患者の約3割が受けており、「再現性(毎回同じ体位)の確保」「治療の完遂」と、出現する有害事象(副作用)の予防・早期発見・対処が大切です。入院時は、病棟看護師と連携・協働して看護ケアやセルフケア支援を行い、外来通院時は、治療棟看護師が、患者自身でセルフケアを行えるように「自己管理表」を使いサポートします。そして、治療と向き合えるように気持ちに寄り添い、院内の他チームとも連携を密にし、必要な情報を整理して意思決定支援等を行います。これからも放射線療法を選択した人々の身近な存在として出来ることを看護スタッフと共に考え、放射線療法看護の質の向上と安定を目指していきます。

埴 瀬里奈がん薬物療法看護

埴 瀬里奈認定看護師
抗がん剤治療を受けている方の希望に寄り添いたい
患者さんが安心して治療を受けるためには、薬剤の特徴や投与管理、副作用マネジメント等に関する正しい知識やケア方法を身につけることが大切です。歩き方や表情といったささいな様子から、身体面や精神面などの「普段と何か違うかも?」に気付き適切なケアにつなげられるよう専門的知識や実践力を活かしながらスタッフと共に成長していきたいです。
治療を頑張ってもう一度好きな物を食べたい、家族と旅行に行きたい、愛犬と散歩に行きたい、など患者さんによって治療を頑張る理由はさまざまです。そんな患者さんの希望を支えていけるよう、患者さんやご家族はもちろん、院内外のスタッフも気軽に相談のできる身近な存在でありたいです。

髙橋 ゆか摂食・嚥下障害看護

髙橋 ゆか認定看護師
「食べたい」という思いに寄り添う看護
摂食・嚥下障害看護とは加齢や成長発達、疾病・治療の副作用により「食べる」機能に障害が生じた方の、人生の大きな楽しみの1つである「食べたい」という思いに寄り添う看護です。摂食嚥下の分野はがん治療や脳血管疾患、神経筋疾患、認知症、高齢者、サルコペニアなど多岐にわたります。現在入院期間の短縮により摂食嚥下障害を持ちながら自宅退院や転院、施設入所をする方が増えています。食べるリハビリに苦悩する患者さんや、家での食事や口腔ケアに不安を抱える患者さんとご家族の支えになりたいと考えています。
そしてリスク管理をしながらも1日でも早く、長く安全に、食べたいものを食べることができるように、多職種と連携しながら支援していきたいです。

牧野 路子がん看護

牧野 路子専門看護師
最善のために、迷いを支える
がん患者さんとそのご家族は、治療の選択、がんやがん治療に伴う症状の出現、仕事や家庭の調整、再発の不安など複雑な思いを抱え生活しています。また、症状緩和に難渋し死と向き合う患者さんを間近でケアするスタッフも苦悩を抱えています。どんな状況でもその人らしく生きるために一歩踏み出す勇気を持ちたいという思いからがん看護専門看護師をめざしました。生きることにこだわり、何がよりよい選択・ケアなのか、患者さんとご家族やケアするスタッフと一緒に悩み考えともに歩む存在でありたいと思っています。

山根 恵小児救急看護

山根 恵認定看護師
子どもと家族の思いに寄り添うこと
小児救急看護認定看護師は、子どもの身体状況のアセスメントを確実に行い緊急度の判断をしたり育児不安や虐待への対応、家庭における初期対応指導、子どもの事故予防指導などの役割を担っています。そのため、救急対応はもちろんのこと、家庭における育児能力の向上といった観点も考慮しながら関わる必要があります。子どもは自分の思いや訴えをうまく言葉で表現できないことが多く、家族もまた何らかの思いを抱いて受診しています。その気持ちに寄り添い支援することは子どもと家族が安心・安全に生活していくことに繋がると考えます。「子どもの権利を守る」という視点で、子どもの健やかな成長発達のために家族を含めた支援を続けていきたいと考えています。

伊藤 宏之小児救急看護

伊藤 宏之認定看護師
For the future of Children
小児救急看護認定看護師は、小児救急医療における子どもと家族の権利を擁護し、自己決定を尊重した看護を実践します。子どもと家族のニーズに対応し、年齢・発達に応じた家庭での初期対応から救命技術までの身体的なケアから、危機状況にある患者及び家族への精神面の看護まで、患者や家族の状態、緊急度・重症度 をアセスメントし、確実な看護技術を実践することを活動の目的としています。
また医療処置やケアをもち在宅療養に移行する子どもと家族が、安全な在宅療養できるようにも支援をしています。

西本 尚弥脳卒中リハビリテーション看護

西本 尚弥認定看護師
患者さんや家族の思いを尊重して
脳卒中とは、脳梗塞・脳出血・くも膜下出血の3つに分類されます。脳卒中を発症すると、意識障害や運動麻痺、記憶障害などの高次脳機能障害といった障害を併発することで、その人の人生が一変してしまう病気で、現在寝たきり第1位の原因となっています。
脳卒中を発症した患者さんは、障害が原因で自分の思いを訴えることができなかったり、またその患者さんを支える家族も今後の生活に強い不安を抱いてます。日々の関わりの中で、患者さんや家族の思いに寄り添い、他職種と共同し、一緒に考え、「その人らしい生活」が送れるよう、看護実践を行っていきたいと思います。

藤田 久美子脳卒中リハビリテーション看護

藤田 久美子認定看護師
患者さんの生活の再構築に向けて
脳卒中は脳の血管が詰まる「脳梗塞」脳の血管が破ける「脳出血」脳の血管にできた動脈瘤が破裂する「くも膜下出血」があり、何らかの障害を残すこわい病気で、介護を必要とする原因の上位を占めています。 突然発症し、生活が一変してしまう患者さんやご家族に出会い自分の無力さを感じ、認定看護師を目指しました。生命の危機を乗り越え、患者さんのもう一度喋りたい、食べたい、歩きたい、トイレに行きたいといったその人らしい生活の再構築に向けて寄り添う看護に携わることが出来ることに喜びを感じています。

由比 宏和慢性呼吸器疾患看護

由比 宏和認定看護師
「自分らしく」をサポートする一員として
私たちは普段何気なく呼吸を行っています。しかし慢性呼吸器疾患患者はCOPD・気管支喘息・間質性肺炎など様々な病気によって呼吸器に障害が生じているため「息が辛い」という体験や精神的疲労を抱えながら日々の生活を送っており、在宅療養を行う中で、自己管理はとても大事になってきます。
内服・吸入、酸素療法などを行いながら病気の増悪を予防し、「自分らしく」を目標に自己管理し在宅療養生活を送ることができるようサポートしていきたいと思っています。

加納 恭子皮膚・排泄ケア

加納 恭子認定看護師
身近なパートナーとして寄り添う看護を
高齢化や最新医療の発展と共に、看護の現場には様々なスキントラブルが発生しています。 普段よく見かける発赤や糜爛は、まずは予防的ケアを行い、発生後は根拠に沿ったケアを行えば早期治癒が可能です。私が認定看護師を目指したのは、スキントラブルを繰り返すストーマ造設後の患者さんに対するケアや精神的苦痛へ援助方法がわからず、アセスメント能力の未熟さを感じたことがきっかけです。創傷、ストーマ、失禁ケアの3分野を、患者さんや家族のライフスタイルを考慮した上で、専門的視点からスタッフと共にケアの方法を考え、優しい看護を提供していきたいです。

松山 千夏感染管理

松山 千夏認定看護師
進化した病棟改革
「手洗い」といった標準予防策をはじめ、感染対策を実践していくことは、患者さんだけでなく、医療スタッフの安全のためにも大切なことです。感染管理に関する知識や技術を習得してから、専門的な視点から問題となっていることや必要なことを見出し、スタッフと日々考えながら実践していけることにやりがいを感じています。これからも病院全体がレベルアップできるよう創造と進化をモットーに、時には役割モデルとなり現場レベルで実践できる刷新的なアイデアを生み出し活発に活動していきたいです。

西村 一美感染管理

西村 一美認定看護師
アンテナを高くする
感染管理は、目に見えない細菌やウイルス、そして様々な人の考えが相手になります。相手が目に見えないということは難しいですが、スッタフに時間をかけて繰り返し基本的な感染対策や教育を行い、いつの間にかスタッフそれぞれが、患者さんに合わせた感染対策を実践しているとき、やりがいを感じます。
感染管理には日常業務でおかしいな、変だなと思うアンテナを高くしておくことが必要です。 そこで皆さんと、どんな些細な疑問でも一緒に話していくことから始め、感染管理に取り組みたいと考えています。

中西 美穂子糖尿病看護

中西 美穂子認定看護師
患者さんの笑顔のために、共に考え、支えていく。
糖尿病の治療は、薬物・食事・運動療法が基本であり、生活をしながら生涯に渡って患者さんが主体的に治療を継続していく事が必要になります。そこには、治療を継続していくことの困難さや辛さ、時には治療を投げ出したくなるようなこともあると思います。患者さんの生活背景や役割を十分に考え、患者さんや家族の生活や気持ちに寄り添い、共に考えながら、一人一人に沿った支援ができるように取り組んでいきたいです。そして、少しでも多くの患者さんが、糖尿病を持ちながらでも、その人らしく生き生きと過ごせるようになることが目標です。

出口 文代新生児集中ケア

出口 文代認定看護師
共に学び、看護の楽しみを感じる。
新生児看護は、出生直後から集中的な治療を受ける新生児に対し、人として尊重し人生の始まりに寄り添い、新生児の声なき声に耳を傾け、より良い看護を提供できるよう根拠を踏まえた最新の専門的知識・技術を活かした看護展開を実践し、家族の始まりを支え、寄り添い、新生児の成長・発達を家族と一喜一憂しながら信頼関係を築くことです。
学ぶ姿勢を忘れず、日々疑問に思ったことを追及する姿勢はとても大切です。一緒に看護の醍醐味を感じながら、やりがいを見出してみませんか。

宮川 久美子手術看護

宮川 久美子認定看護師
終わるまで、ずっと側にいて守る。
今よりも少しでも良い未来をめざして手術を決断し、勇気を振り絞って手術室に来られる患者さんを、手術が終わるまで、ずっと側にいて守るのが私たち手術室看護師の役目です。手術中は色々な危険が起こる可能性があります。それを1つ1つかいくぐり、手術を終えて無事に家族のもとに戻っていただけるように、医師・看護師・臨床工学技士・検査技師・放射線技師らが手術チームとして一丸となって役割を果たすことが重要です。チームの誰よりも患者さんの味方として安全・安楽を確保できるよう専門性を高め、手術チームを円滑に動かすための潤滑油となれる手術室看護師を目指して、一緒に頑張りましょう。

木村 夏希手術看護

木村 夏希認定看護師
よりそい、手術をともにのりきる
手術は患者さんにとって大きなライフイベントです。手術、麻酔、術後、生活と様々 な不安を抱えつつ、手術に挑みます。以前、患者さんに廊下で「ありがとう」と声をかけて頂いたことがあります。数日前に手術を受けた患者さんでした。関われる時間はとても少ないですが、手術を前に極度の緊張や不安の中にある患者さんにとってはそれだけ印象に残る時間なのだと実感しました。
手術を受けられる患者さんに少しでもよりそえるよう、術中だけでなく病棟や外来と連携し、切れ目のない看護を実践し、多職種で構成される手術チームで患者さんの安全を守ります。術前から術後を通して、患者さん自身がどうなりたいかをともに考えられる看護師を目指しています。

丸木 裕美認知症看護

丸木 裕美認定看護師
「生きるとは」をともに考えさせていただく
認知症を患う方が新たな疾患を抱え入院されます。現状を理解することが難しいことも多い認知症の方々は慣れない環境の中、大きな不安を抱え、混乱されることもしばしばです。そのような中で、一番近い存在である看護師の関わりで安心して過ごしていただけると考え、どのような関わりが必要なのかを病棟スタッフとともに考えています。
また、経験豊富な人生の先輩方が今何を思い、どこでどのように過ごされたいと考えておられるのかを伺いながら、ご本人、ご家族とともに退院後の生活を考えようと日々努力しています。

橋本 文認知症看護

橋本 文認定看護師
ニードは何か考える
認知症の方々にとって、入院の環境は自宅とはかけ離れており、その環境の変化は混乱をもたらします。しかし、馴染みの物を置き、自宅に近い環境に近づけたり、看護師が患者さんのニードを把握し関わる事で、落ち着いた入院生活が遅れるようになります。そのような、入院生活を送っていただけるよう、患者さんに関わっていくことが私の理想です。また、治療や療養場所の選択など認知症の方々の意思を尊重した支援ができるように取り組んでいきたいと思っています。

山下 紗也加慢性心不全看護
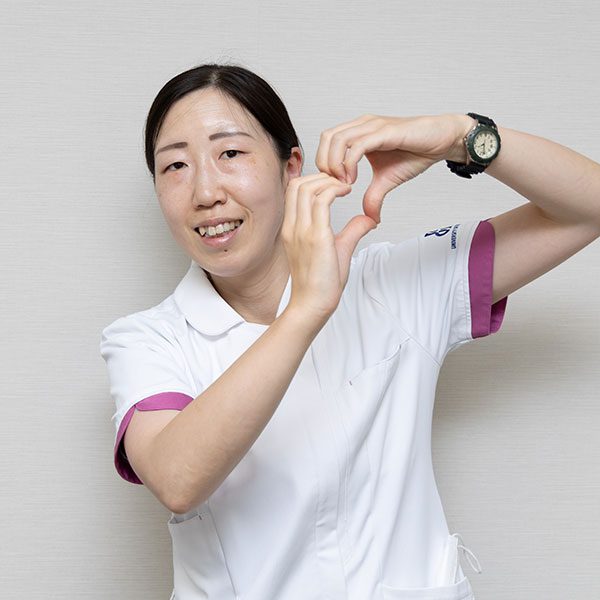
山下 紗也加認定看護師
心不全と上手に付き合うためにできること
心不全は全ての心疾患の終末像と言われ、悪くなったり、少しよくなったりを繰り返し、徐々に病状を悪化させていきます。私の役割は心不全を悪くさせる原因を特定、観察し、重症化の回避や回復の促進、再発を予防するための指導を行い、在宅療養を見据えた生活調整を行うことです。患者様によっては息切れや体のだるさが残ることがあり、症状と折り合いをつけて生活ができるよう支援を行います。心不全と付き合っていくには様々な制限が課されてしまい、これまでの生活習慣を改善しなければなりません。少しでも患者様の不安を減らし住み慣れた家で長く過ごすことができるよう、一緒に考えサポートしていきたいです。