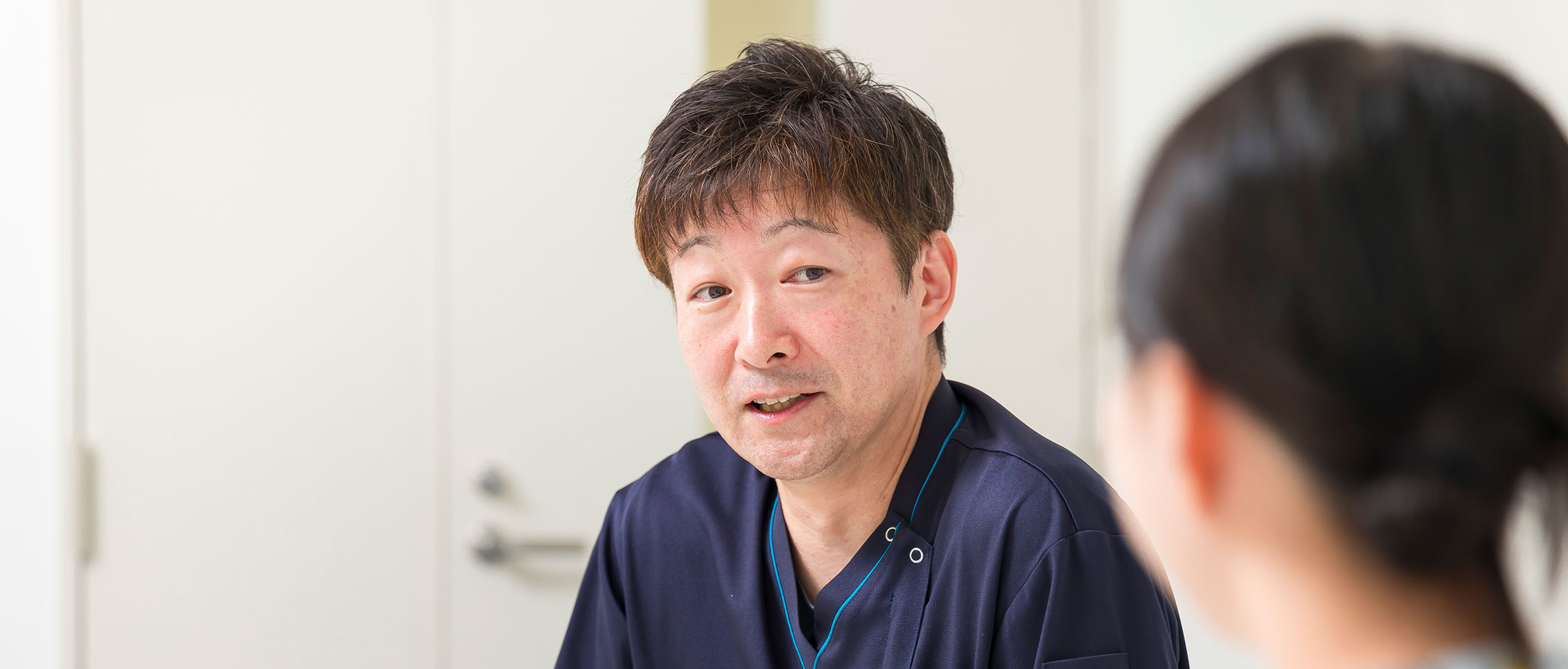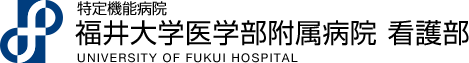TOPICS 01
「対話」はどうして大事?
チーム力を発揮して医療と看護の質を上げよう

以前、勤務していた病院でもPNSを導入していたんですよ。ただ、そちらではまだ導入したばかりで、本院へ来てから本格的にPNSのもと働くことになって。

どんな違いがありましたか?

本院は対話を大事にしているな、と。PNSの難しいところって、パートナーと何でも言い合える対等な関係づくりだと思いますが、対話をしっかりすることで、パートナーシップを築けている。

わかります!長年の風土みたいなものもあるのかな。お互いに尊重し合って、意見を言うべきところは言う。情報共有の意識が根付いています。それがより個別性の高い看護につながっていくので、患者さんにとってもメリットが大きい。

PNSのパートナーはもちろん、医療チームは医師や薬剤師、診療放射線技師など横のつながりも大事。多職種が連携して、建設的な意見を出し合うことで、ベストな医療を提供できますから。PNSは医療チーム全体の質を上げるのにも一役買っていると感じるな。

以前、勤務していた病院ではチームナーシング体制を導入していて、チーム制のもと、基本的に1人で患者さんのケアをしていました。その頃は成人病棟勤務だったので、今とはケアの方法も違って。こちらへ来て、小児科に配属された時はPNSがあったので、とても助けられました。

TOPICS 02
救急部と小児科のPNSとは?
「患者さんのために」という気持ちで

どんなにキャリアを積んでも、パートナーとダブルチェックができる環境って心強いですよね。Nさんみたいに違う科へ異動になっても、PNSがあればパートナーから知識を得て、仕事を覚えやすいし。

ただ、ひとつ大変だったのはスケジュールの決定ですね。以前の病院ではスケジュールも自己完結していたので、パートナーとの調整に慣れるのに少し時間がかかったかな。でも、それも情報共有をしっかりすれば、乗り越えられます。

小児科で、PNSがあって良かったと思うのはどんな場面?

点滴をする時、怖がってしまうお子さんもいるので、1人があやして、もう1人が針を指す。パートナーがいないと大変なんですよ。ご家族との関わり方にしてもパートナーの話し方が参考になったり。

チームプレーのいいところですね。救急部では患者さんの状態が一刻一刻変化していくこともあるので、1人が処置しつつ、もう1人が記録をリアルタイムに記入できると、安心感がある。片方が処置に集中できるので。

科が違うと、ケアも違いますが、カバーし合える良さは同じですね。それが患者さんのためになっている。

TOPICS 03
後輩から教えられることも!
意見を言い合える環境を整える

私たちはキャリア的に中堅なので、先輩の立場でパートナーと接することが多いですよね。そこで、課題となってくるのが指導力。先輩が後輩と接する時、指導力の差をどうするのか。

昨年、リーダーシップ研修を受けて、今年から新人教育の中心的存在であるクリニカルコーチになりました。教育で大事なのは、やっぱり対話。相手の意見を聞いて、対話をするように心掛けています。

管理職研修にもその視点が取り入れられていますよ。すべて答えを教えるのではなく、振り返りをして相手の意見を引き出す。相手の思いを尊重しつつ、意見が言いやすい環境づくりをしていかないと。PNSと同時進行で、指導者の育成にも注力していくべきなんじゃないかな。

クリニカルコーチになって、私も新しい知識を吸収しないといけない。新人の質問を受けることで、気づかされることもありますし。指導を通して、自分も成長できています。

新人の質問を受けて、「一緒に調べてみよう」という考え方って大事。「教えてあげる」という気持ちが強いと、それが負担になってしまう。先輩のパートナーとしてスキルを伝えつつ、一緒に成長していく。指導する側のスキルをベースアップできれば、PNSはさらにうまく機能すると思います。