脳神経内科
中枢神経から末梢神経・筋肉に及ぶ病気を幅広く担当し、診療しております。脳血管障害、神経変性疾患、免疫性神経疾患、神経感染症などが主な疾患です。意識障害、めまい、頭痛、しびれ、ふるえ、運動障害、歩行障害、物忘れなど、日常的に頻度の高い症状を起こした患者さんを積極的に診療しています。

診療体制・治療方針
2025年1月、西山康裕教授を迎え、新たな体制となりました。以前より当科は脳神経外科と協働して一次脳卒中センター・コア施設として24時間356日、血栓溶解療法および血栓回収療法を行ってきましたが、より積極的に急性期治療を行い、かつ再発予防、発症予防に努めています。また、当科には神経内科専門医、総合内科専門医、脳卒中学会専門医、認知症学会専門医、臨床遺伝専門医が在籍しており、県内唯一の大学病院として、神経難病の診断、治療を行っています。原因不明の神経・筋疾患についても丁寧な病歴聴取と身体診察、核医学検査を含む画像検査、電気生理学検査、生検(脳、末梢神経、筋)、遺伝学的検査を駆使して、正確な診断に努めています。長年、治療法がないと言われてきた神経・筋疾患ですが、近年では多彩な分野で治療薬が開発され、生物学的製剤や酵素補充療法、さらには遺伝子治療が登場し、大きな変革が起きています。完治とはいかないものの症状の緩和や生命予後の延長が図れるようになってきており、最新の治療を積極的に導入しています。診断・治療にあたっては多職種協働が要であり、脳神経外科や循環器内科、リハビリテーション科、放射線科、高エネルギー医学研究センター、看護部、地域連携室など多くの部署と日常的に密にコミュニケーションをとって、患者さんによりよい医療と生活支援の提供に尽力しています。
得意とする分野
一次脳卒中センター(PSC)・コア施設として24時間356日、血栓溶解療法および血栓回収療法を提供できる体制を整えています。後遺症の軽減のため積極的に治療を行っていますが、“時短”が重要であり、できるだけ早い受診をお勧めください。また、当院には厚生労働省からの指定により福井県脳卒中・心臓病等総合支援センターが設置されており、患者さん・ご家族に対する支援、市民啓発活動、さらに地域の医療機関・各医療専門職との連携など、包括的な支援を行っています。(https://www.fukui-noushincenter.jp/)
認知症については、病歴聴取と神経心理検査を行い、血液検査、脳MRI検査、脳血流SPECT検査をまず行っています。特にアルツハイマー病を疑う場合は、高エネルギー医学研究センターと協力し、最新のアミロイドPET検査を行って的確に診断し、軽度認知障害(MCI)~早期アルツハイマー型認知症の患者さんには厚生労働省の適正使用推進ガイドラインに則って抗アミロイドβ抗体薬を導入しています。(PET検査ができない場合には脳脊髄液検査を行います。)
意識障害、けいれんなどの患者で自己免疫介在性脳炎・脳症が原因であることがわかってきています。治療には濃密な免疫治療が必要となることも多く、通常診療では困難な治療を提供しています。原因として多数の自己抗体が報告されていますが一般的な検査ではありません。当院では専門研究機関に依頼し、原因究明を積極的に行っています。
高度医療
24時間365日の体制で、発症・発見から4.5時間以内の超急性期脳梗塞に対して、積極的に血栓溶解療法(rt-PA静注療法)を行っています。加えて、脳神経外科と協働して血栓回収療法を行っています。
神経免疫疾患に対して、副腎皮質ステロイド薬大量点滴静注療法や免疫グロブリン大量点滴静注療法、あるいは血液浄化療法を早期から行い、速やかな病勢コントロールを図っています。近年は免疫チェックポイント阻害薬の普及に伴い、副作用としての神経・筋症状も増加しています。主診療科と連携して、免疫治療で副作用のコントロールを図っています。
パーキンソン病に対して、薬物治療に抵抗性となった場合には、脳神経外科と協働して脳深部刺激療法を導入しています。
軽度認知障害~早期アルツハイマー型認知症に対して、高エネルギー医学研究センターと連携して最新のアミロイドPETを行いアミロイド陽性者に対して抗アミロイドβ抗体薬を導入している。
原因不明の神経・筋症状を呈する患者さんに対して、遺伝性疾患が疑わしいときは、遺伝診療部と連携して遺伝カウンセリングを行い、遺伝学的検査を行っています。症例に応じて未診断疾患イニシアチブ(IRUD)とも連携して診断の確定、病態解明、治療につながるように尽力しています。
症状・対象疾患
中枢神経(脳・脊髄)~末梢神経~神経・筋接合部~筋肉に生じる疾患が対象です。
症状例:顔や手足の脱力やしびれ、しゃべりにくい、頭痛、めまい、歩行時のふらつき、動作緩慢、意識が悪い、けいれん、物忘れ疾患例:脳血管障害、脳炎、髄膜炎、自己免疫介在性脳炎・脳症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、多発性硬化症、重症筋無力症、ギラン・バレー症候群、筋萎縮性側索硬化症、皮膚筋炎、筋ジストロフィー、ミトコンドリア病、てんかん、認知症、片頭痛、末梢神経障害を伴う膠原病 など
神経や筋の症状を訴える患者さんはお気軽にご相談ください。
主な検査と説明
脳血管障害の病型診断と最適な治療法を選択するため、MRI・MRA、頸動脈エコー、経食道心エコー、下肢静脈エコー、経頭蓋エコー、脳血流SPECT検査を駆使しています。また、近年、心原性脳塞栓症が増加しており、循環器内科と協力してホルター心電図やループ心電計を用いて、発作性心房細動の検出に努めています。
当科の特有な検査としては、電気生理学的検査が挙げられます。てんかんや意識状態の評価に脳波検査を用いています。神経伝導検査(反復刺激試験を含む)、筋電図検査を用いて、末梢神経疾患、筋疾患のほかに、筋萎縮性側索硬化症、神経筋接合部疾患(重症筋無力症など)や神経根病変(椎間板ヘルニアの高位診断など)を行っています。これらの結果によって、神経生検、筋生検でもって病理学的検査を行います。
パーキンソン病と類縁疾患に関して、DaT-SPECTやMIBG-心筋シンチグラフィといった補助診断も活用して正確な診断に努めています。
アルツハイマー病の検出には、アミロイドPET検査や脳脊髄液検査を行っています。


科長・スタッフ紹介

神経・脳血管障害

神経
| 助教・外来医長 | 山口 智久 | 神経・遺伝 |
| 特命助教 | 浅野 礼 | |
| 医員 | 高久 直子 | |
| 医員 | 臼井 宏二郎 | |
| 医員 | 内田 待望 | |
| 医員 | 江口 茉優 |
兼任
| 教授(地域医療推進講座) | 山村 修 | 神経・脳血管障害 |
| 教授(地域健康学講座) | 井川 正道 | 神経・遺伝 |
学会等認定制度による施設認定
| 学会等名 | 事項 |
|---|---|
| 日本神経学会 | 専門医制度教育施設 |
| 日本認知症学会 | 専門医制度教育施設 |
| 日本脳卒中学会 | 専門医制度教育施設 |
外来診察予定
令和7年7月~
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 【初診・再診】 井川 正道 高久 直子 担当医 〔脳神経内科の診断と治療〕 |
【初診・再診】 西山 康裕 佐々木 宏仁 〔脳神経内科の診断と治療〕 |
【初診・再診】 榎本 崇一 安川 善博 〔脳神経内科の診断と治療〕 |
【初診・再診】 山村 修 〔脳神経内科の診断と治療〕 |
【初診・再診】 山村 修 山口 智久 〔脳神経内科の診断と治療〕 |
| 午後 | 【初診・再診】 林 浩嗣 〔物忘れ外来〕 |
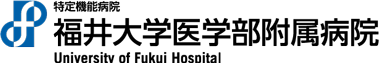
 福井大学
福井大学 0776-61-3111
0776-61-3111
 交通
交通 フロア
フロア 診療科・部門のご案内
診療科・部門のご案内